次の記述のうち正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
1.( )
|
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項
に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
|
2.( )
|
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行う。
|
3.( )
|
国民年金事業は、政府が、管掌し、事務の一部を、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団、市町村長(特別区の区長を含む。)に委任することができる。
|
4.( )
|
年金額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられるよう努めなければならない。
|
5.( )
|
国民年金事業の財政は、恒久的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
|
|
|
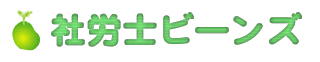
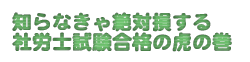
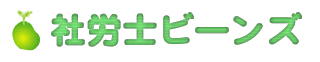
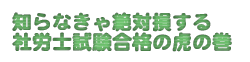
![]()